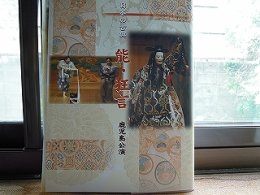こだわりの芋焼酎を鹿児島から全国へお届け
ショッピングカート
カートの中身
カートは空です。
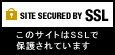
|
ホーム |
店長日記
店長日記
店長日記:634件
試飲・即売会のお知らせ
仇討
金木犀
神無月
硫黄島顕彰慰霊祭(出水)・・・・・・・1
彼岸
敬老の日
高砂(観世流)
御月見
9:11
土石流
時代屋の女房
長月
白熊
蝉
お盆
水泳
同窓会
姥ユリ
葉月
|
ホームページ作成とショッピングカート付きネットショップ開業サービス