店長日記
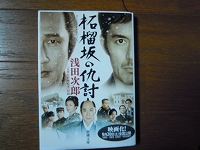
柘榴坂の仇討
2014年10月25日
先日、映画「柘榴坂の仇討」を観ました。
腕に覚えのある志村金吾なる侍が井伊大老の御籠回り近習の役に取り立てられたものの桜田門外の変にて主君を守れず、その責めを負い、父が切腹、母は喉を突いた上は、金吾自身には切腹も許されず、主君の仇討を命ぜられるものの十三年歳月が流れ、時は明治となり、仇・佐橋十兵衛を見つけたその日に仇討禁止令が発布されます。 かつて桜田門にて敵味方として戦った者が再会し舞台は、柘榴坂へ。刀を抜いたものの互いに命を取ろうなどといった気持ちはなく、歳月は十三年経とうとも、ふたりとも時が止まったまま。金吾は雪の桜田門の彦根橘の御駕籠のかたわらに立ちつくし、十兵衛もまた自訴し命を終えるつもりがこの世に背を向け生きてきました。お互いが、心に傷を負いもがきながらも、井伊大老の御心を思うなら「生きる」ことを選択します。
歴史的には悪名高き井伊大老ですが、茶人としての評価はとても高く、映画の中でも風流な一面が描かれています。中村吉衛門さんがそこのところを見事に演じており、ここが伝わらないと、時代が明治となり、家禄も名も旧に復すこはずはないのに、金吾が仇討に固執した理由「拙者は、掃部頭さまが好きでござりました。」という一言が生きてきません。
私の父も学生時代、京都にて、お茶を習っていたそうです。私は表千家か裏千家とばかり思っていました。父に流派を尋ねたところ「近江石州流。」と父は答え、「茶人として井伊大老は一流だった。」と言いました。父は鼓も習っていたそうで、映画の井伊大老を見て、父の言葉を思い出しました。
もうすぐちちの一周忌です。御駕籠の前に立ちすくんでいるのは自分のような気がして、とても心に残る映画となりました。
の手おtyを
腕に覚えのある志村金吾なる侍が井伊大老の御籠回り近習の役に取り立てられたものの桜田門外の変にて主君を守れず、その責めを負い、父が切腹、母は喉を突いた上は、金吾自身には切腹も許されず、主君の仇討を命ぜられるものの十三年歳月が流れ、時は明治となり、仇・佐橋十兵衛を見つけたその日に仇討禁止令が発布されます。 かつて桜田門にて敵味方として戦った者が再会し舞台は、柘榴坂へ。刀を抜いたものの互いに命を取ろうなどといった気持ちはなく、歳月は十三年経とうとも、ふたりとも時が止まったまま。金吾は雪の桜田門の彦根橘の御駕籠のかたわらに立ちつくし、十兵衛もまた自訴し命を終えるつもりがこの世に背を向け生きてきました。お互いが、心に傷を負いもがきながらも、井伊大老の御心を思うなら「生きる」ことを選択します。
歴史的には悪名高き井伊大老ですが、茶人としての評価はとても高く、映画の中でも風流な一面が描かれています。中村吉衛門さんがそこのところを見事に演じており、ここが伝わらないと、時代が明治となり、家禄も名も旧に復すこはずはないのに、金吾が仇討に固執した理由「拙者は、掃部頭さまが好きでござりました。」という一言が生きてきません。
私の父も学生時代、京都にて、お茶を習っていたそうです。私は表千家か裏千家とばかり思っていました。父に流派を尋ねたところ「近江石州流。」と父は答え、「茶人として井伊大老は一流だった。」と言いました。父は鼓も習っていたそうで、映画の井伊大老を見て、父の言葉を思い出しました。
もうすぐちちの一周忌です。御駕籠の前に立ちすくんでいるのは自分のような気がして、とても心に残る映画となりました。
の手おtyを